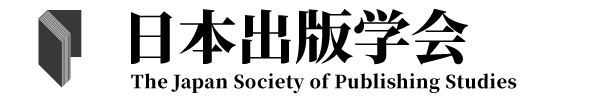■日本出版学会 第9回 MIE研究部会 開催報告
「MIEを実践する教員の「成果と課題」
―― MIEの狙い・成果・評価・悩み」
第9回MIE(雑誌利活用教育)研究部会では、野上勇人会員(開志専門職大学)、森貴志会員(梅花女子大学)、元永純代会員(跡見学園女子大学)が「大学における雑誌制作教育」の実例を報告した。司会・進行は牛山佳菜代会員(目白大学)が務めた。
森会員は、ゼミで制作している雑誌『colors』について報告した。同誌は2024年度「日本地域コンテンツ大賞」MIE部門において優秀賞を受賞している。森会員は、「学内や取材先から雑誌としての完成度が高いと評価を得ている」と述べ、MIEの狙いとして「雑誌以外のメディアにも応用できる表現技術が習得できること」「手を動かすことで学生が達成感を得られること」などを挙げた。一方で、課題として予算面を指摘し、今後はコスト削減を見据えた方法も検討しなければならないと述べた。
元永会員は、ライティング特殊演習の授業で制作している『Visions』について報告した。デザイン、撮影、校正、印刷といった各工程を学外の専門家に依頼しており、「学生がプロフェッショナルと共にものづくりを行うことが本誌の狙い」であると述べた。雑誌制作の技術習得よりも、制作プロセスを通じたチームワークや協働経験を重視しており、完成後には制作過程をまとめた冊子も作成している。課題としては、「現状、企画立案を教員が担っているが、本来は学生に行ってほしい。ただし、通年28回の授業内でその時間を確保するのが難しい」と述べた。
野上会員は、前任校の東北芸術工科大学および現職の開志専門職大学において、地域情報誌、市販文芸誌、オープンキャンパス配布用のゼミ冊子・作品集、外部団体からの依頼によるPR誌など、多様な雑誌づくりを指導している。大学で編集を教える際には、「学生が企画、原稿執筆、撮影、デザイン、DTPをすべて自分たちで行うことを前提とし、教員もそれらを指導できるよう準備する必要がある」と述べた。学生の主体性を高めるため、企画立案からスケジュール管理まで全工程を学生が担う体制をとっており、これは出版教育にとどまらず「コンテンツ制作人材の育成」を見据えた取り組みであると語った。
質疑応答では、「雑誌を読む学生の減少」「文章力を高めるための指導」「学科ごとに異なるMIEの狙い」などについて活発な議論が行われた。
清水一彦会長からは「工夫に満ちたMIE実践例を聞き、MIEの未来は明るいと感じた」との講評があり、本多悟会員からは「雑誌市場は縮小傾向にあるが、表現手段としての雑誌やZINEは再評価されている。MIEがコンテンツ制作人材の育成に寄与していることは確かである」と総評があった。
今回の研究部会は報告中心の構成で、ディスカッションの時間を十分に確保できなかったが、各実践報告からは、MIEが指導者ごとに多様な形で展開されていること、統一的なマニュアルは存在しないものの、共通して「雑誌づくりを通じて広いコンテンツ制作能力や主体性を育む」教育実践であることが明らかになった。
今後は、MIE実践における課題に焦点を当て、現場での指導経験を共有しながら、解決策の模索を続けていきたい。
日 時: 2025年9月2日(火) 午後5時00分~6時30分
開催方法:会場での対面形式とZoomによるオンラインの同時開催
会 場: 跡見学園女子大学 文京キャンパス 2302教室
参加者: 15名(会員15名。うち、オンライン参加者5名)
(文責:元永純代)