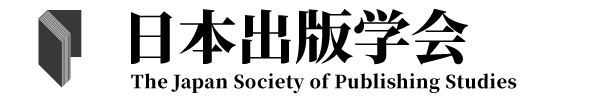第44回 日本出版学会賞審査報告
第44回日本出版学会賞の審査は、「出版の学術調査・研究の領域」における著書を対象に、「日本出版学会賞要綱」および「日本出版学会賞審査細則」に基づいて行われた。今回は2022年1月1日から同年12月31日までに刊行・発表された著作を対象に審査を行い、審査委員会は2023年2月13日、3月16日の2回開催された。審査は、出版学会会員からの自薦他薦の候補作と古山悟由会員が作成した出版関係の著作および論文のリストに基づいて行われ、その結果、日本出版学会賞奨励賞2点を決定した。また、清水英夫賞(日本出版学会優秀論文賞)の審査を行い、第4回清水英夫賞1点を決定した。
なお、日本出版学会編『パブリッシング・スタディーズ』は、学会自身による著作のため学会賞の候補作とはしないが、現時点における出版研究の集大成であり、今後のための方法論を構築した論集として意義のある著作であると認められるものである。
【奨励賞】
大尾侑子 著
『地下出版のメディア史――エロ・グロ、珍書屋、教養主義』
(慶応義塾大学出版会)
[審査報告]
戦前日本における「エロ」「グロ」の地下出版界のあり様を精緻に分析し、メディア史研究の領域に「軟派出版史」という新生面を開いた本書は、従来アカデミックな研究の枠外に置かれていた対象を、出版産業(出版社)ネットワークと人的ネットワークの両面から研究し、独自性の高い成果をもたらしている。
学会賞審査委員会で選考をおこなった結果、個々の出版物の内容をセンセーショナルに扱うのではなく、形式や関連資料の情報も網羅的にまとめている点において、出版研究としての完成度の高さが評価された。また、独自調査による資料収集が多岐にわたる点、そこから導かれる文化の「高級低級」「軟派硬派」といった複層的な価値観についての発見が示されている点で、今後のメディア研究においても風俗研究においても、基本資料となり得ることが高く評価された。
一方で本書は、アカデミックな研究の枠外にある対象をアカデミック側に取り込むことによる、社会的コンフリクトのまさに中心となった論考でもある。そうしたコンフリクトは、アカデミズム対ニューアカデミズムという二項対立を乗り越えて、新たな対話を生む可能性を示すものとして、さらなる成果の広がりに期待を寄せることができるだろう。以上の諸点を踏まえて、本書が日本出版学会賞奨励賞に値すると判断した。
[受賞のことば]
大尾侑子
このたびは由緒ある賞を賜り、誠にありがとうございます。選考にあたり大切なお時間を頂戴した先生方をはじめ、今日までご指導くださった方々に、この場を借りてお礼申し上げます。残された史料と膨大な先行研究のもと、代表者としていただいた奨励賞だと自覚しています。
授賞式でも申し上げましたが、博士論文を元にした本書が日の目を見ることができたのは慶應義塾大学出版会のおかげです。拙著への評価が“上製、496頁、年表、カラー口絵付き”というワガママな造本――、その威容に支えられていることは疑うべくもありません。出版に際しては日本学術振興会の出版助成にサポートしていただいたことも申し添えます。
そしてなにより、不精な一人の院生を、ここまで懲りずに導いてくださった編集者の村上文さんに感謝します。くしくも同時受賞されました田中美佳先生の『朝鮮出版文化の誕生』も、ご担当されました。お二人とともに受賞のよろこびを共有できたことを嬉しく思います。
さて、拙著が論じた戦前昭和の「地下出版界」とは、発禁を回避すべく会員限定頒布システムを構築した半合法(非合法)的出版物が織りなすメディア文化圏です。一般に内務省への納本義務を無視した出版物は秘密出版と呼ばれますが、本書では「合法/非合法/半合法」が複雑に絡み合い、特殊な人的ネットワークをなした軟派出版の世界を「地下出版」と再定義しました。
そして、彼らが共有した趣味、あるいは教養観とはどのようなものであり、それは同時代の知的風土といかなる関係にあったのか。「メディア史」を掲げる本書ではありますが、根本にあるのはこうしたコミュニティ形成とそこに通底する価値体系を明らかにする社会学的な関心です。そこで手がかりとなったのが、メディアの形式性や物質性、そして見過ごされてきたミニメディアやエフェメラ類でした。たとえば周辺でばら撒かれた内容見本、チラシ、正誤表などこまごました紙物史料とその機能です。そういった意味でこの研究は、メディア論的な関心にも貫かれています。そんな本書が「出版研究」という立場からもご評価いただけたことを、うれしく思います。
最後に拙著の刊行を通じて出会った方々にも感謝をお伝えしたいと思います。2022年、東京古書会館と古書店さんのご協力のもと、家蔵史料を展示した「地下出版のメディア史展」が実現しました。本を補完する重要なイベントとなりました。また古書を愛する皆さま(古本フレンズ!)からは、拙著刊行後に多くのアドバイスと知識を共有していただきました。あたたかな目で研究活動を激励してくださり、勇気の源泉となっています。〈新たな対話〉――、はすでに開かれています。これからも内から湧き出る知的好奇心を枯らさず、いっそう真摯に、かつ健康第一で精進いたします。
【奨励賞】
田中美佳 著
『朝鮮出版文化の誕生――新文館・崔南善と近代日本』
(慶應義塾大学出版会)
[審査報告]
本書は、近代朝鮮の出版文化の形成過程を、同時代の日本出版界との関係と、近代朝鮮の出版文化の基礎を築いた存在である崔南善(チェナムソン)を通して実証的に解明しようとするものである。9章構成で、付表を含めると361頁に及ぶ著者の学位論文を加筆修正したものである。まず序章では新文館の刊行雑誌『少年』の刊行背景を、崔南善の日本体験が及ぼした影響を中心に明らかにしていく。第2章では新文館が『少年』廃刊後に着手した児童雑誌について論じている。第3章では新文館の雑誌の中で最も反響を呼んだ『青春』を、特に多数掲載されている「世界的知識」に焦点をあてて分析している。第4章では当時の朝鮮における女性観や女子教育を取り巻く時代背景を含めて、新文館の刊行物と女性の関係を分析している。第5章では当時の朝鮮では目新しいものであった、シリーズ書籍に焦点をあてて分析している。第6章では1910年代後半に刊行され、ロングセラーとなった『時文読本』について考察している。第7章ではこれまで不明な点が多かった、三・一独立宣言起草により収監された崔南善のそれ以降の活動について、崔が監修した『東明』を通して考察している。最後に終章で第1章から第7章までの知見を整理し、今後の課題にも触れている。歴史研究に必要な一次史料によって実証的な分析を行うという真摯な姿勢に基づく研究である。日本出版学会賞奨励賞に相応しいと考える。
[受賞のことば]
田中美佳
このたびは、素晴らしい賞を賜り大変光栄に存じます。ご選考くださった審査委員の先生方、日本出版学会の方々に心より感謝申し上げます。思いがけず受賞のご連絡をいただき大変驚きましたが、ご評価いただいたことをとても嬉しく思っております。
対象となった拙著『朝鮮出版文化の誕生――新文館・崔南善と近代日本』は、朝鮮初の本格的な出版社である新文館に焦点を当て、近代朝鮮の出版文化の形成過程を同時期の日本の出版界との関係を通して実証的に明らかにしたものです。新文館の設立者である崔南善は、日本ではあまり研究はみられませんが、韓国ではその名を知らない人はいないような存在です。さまざまな顔を持つ人物ですが、本書では特に出版人としての側面に着目しました。
崔南善や新文館の出版物については、韓国を中心に多くの研究が積み重ねられていますが、往々にして一国史的な観点から考察されてきたと言えます。こうした状況を踏まえ、日本の出版界の影響を考慮することで一国史を超える視点を導入することを試みました。明治・大正期の日本の出版物は膨大な量であり、すべてに目を通すことはできませんでしたが、多くの方々の協力を得ながら地道に史料分析や文献の比較・対照作業を続け、なんとか研究成果を本書にまとめることができました。博文館を中心とした当時の日本の出版物がいかに朝鮮に流入し受容されたのか、その過程の一部が明らかになったことを通し、本書が日本の出版・メディア史研究に何か少しでも貢献できていれば幸いです。
今回は日本との関係に着目して考察しましたが、今後は日本だけでなく中国や西洋との関係を含めたグローバルな視点で分析し、続けて越境するメディア史を描いていきたいと思います。また、植民地期を生きた朝鮮の知識人に「出版」の観点からさらに迫っていきたいです。
最後になりますが、本書を世に送り出してくださった慶應義塾大学出版会のみなさまに心よりお礼申し上げます。今回の受賞を励みに、今度もいっそう研究に精進したいと思います。このたびはありがとうございました。
【清水英夫賞(日本出版学会優秀論文賞)】
山中智省 著
「「ライトノベル」が生まれた場所――朝日ソノラマとソノラマ文庫」
(『出版研究』第52号掲載)
[審査報告]
1980年代には「ライトノベルの一源流」を築きながらも90年代にはその勢力を維持することが出来なかった朝日ソノラマ文庫の戦略面に着目し、全盛と衰退を歴史的経緯に添いながら検証するという試みはライトノベルという分野の研究の幅と奥行きを深めた研究といえる。中でも文献調査に加え、おそらくあと10年遅かったら取材が不可能であったと思われる朝日ソノラマに関わった編集者の証言が貴重なデータとなっていることは高く評価したい。対象候補論文の中でも学術論文としての成果と独自性は高く、清水英夫賞に値する。今後の研究にも期待したい。
[受賞のことば]
山中智省
このたびは、拙稿に清水英夫賞を賜り大変光栄に存じます。ご評価を頂きました審査委員の先生方、そして、調査や執筆にご協力を頂きました多くの皆様に、厚く御礼申し上げます。
私がライトノベルの研究に取り組み始めたのは学部生の頃で、折しも、2000年代に到来した商業的ブームの影響下、ライトノベルがアカデミックな研究領域から注目を集め始めた時期でした。そこから数えますと、ライトノベルの研究に取り組んできた期間は、早いもので15年近くになります。とはいえ、新興の研究対象であると同時に、複数のジャンル、メディア、文化の要素を兼ね備えた「複合的な文化現象」ともいわれるライトノベルゆえに、どのような視座や方法でアプローチすべきかについては、長らく模索が続いておりました。こうしたなか、2015年に日本出版学会に入会し、大会や部会における個人研究発表やワークショップの実施のほか、日本出版学会関西部会編『出版史研究へのアプローチ――雑誌・書物・新聞をめぐる5章』(出版メディアパル)への寄稿など、本学会を通じて数多くの貴重な経験をさせて頂いたことは、現在の私の研究に対し、大変多くの示唆を与えてくれました。だからこそ、その成果の一端である拙稿「「ライトノベル」が生まれた場所――朝日ソノラマとソノラマ文庫」にて、学会の名誉ある賞を受賞できましたことは、本当に望外の喜びです。このたびは誠にありがとうございました。
なお、審査報告にてご指摘・ご評価を頂きました編集者の証言については、ライトノベルの萌芽・誕生・発展の過程を検証する上で貴重なデータではありますものの、未だ十分な収集・分析が進んでいない状況にあります。とりわけ、ライトノベルの萌芽・誕生に関与した方々の場合、「おそらくあと10年遅かったら取材が不可能」という事態が差し迫っていることもあって、関係者のオーラル・ヒストリーの収集は今や急務となっています。こうした問題意識は現在、マンガ、アニメ、ゲームの分野でも日に日に高まっており、直近ではPBM(プレイバイメール)に関する資料の保存・整理・公開を目的とした「NPO法人日本PBMアーカイブス」の設立などが記憶に新しいところです。そのため、今後の研究では各種文献資料に加え、ライトノベル(あるいはその源流となり得た小説群)の編集者、作家、読者のオーラル・ヒストリーの収集・分析にも、より注力していきたいと考えております。
今回の受賞を糧に、よりいっそう研究に精進して参りますので、引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。